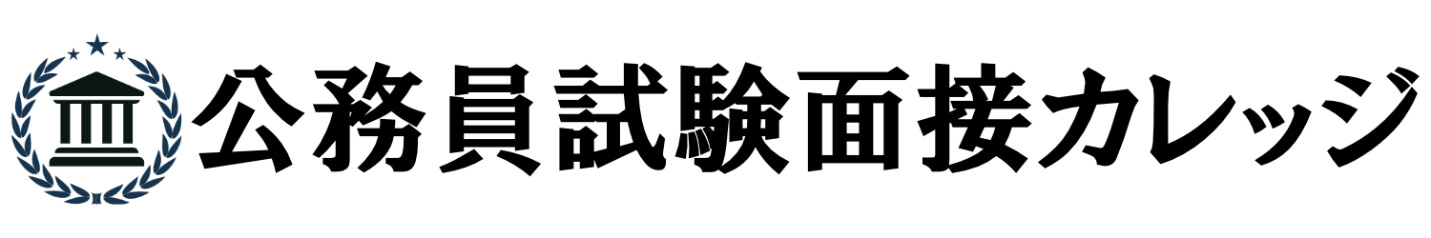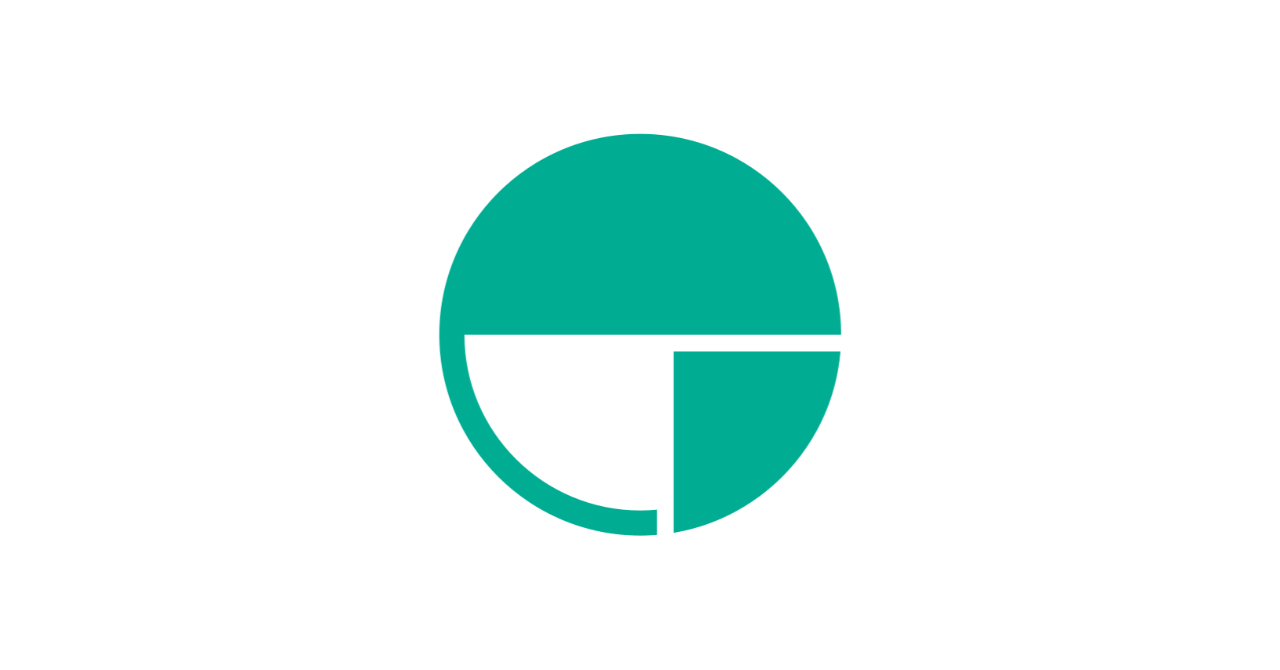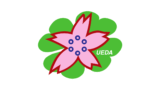長野市役所の面接対策で重要な、市の概要、基本データ、各種産業の特徴、総合計画・基本構想等、近隣自治体について掲載しています。
公務員試験の面接対策においては、まずは志望自治体に関連する基本的な情報を押さえることが大切です。
面接で聞かれ得るというのはもちろんですが、志望自治体や業務への理解を深めるために大いに役立つからです。
そして、そうした情報を面接での回答に活用することができれば、面接官に対してより説得力のある説明ができることでしょう。
この記事を通して志望自治体ならではの特色を理解し、ぜひ面接対策に活かしてください。
なお、その他の自治体については下記の記事からご確認いただけます。
市の概要
 市の全体像を把握するため、長野市の概要について整理しておきましょう。
市の全体像を把握するため、長野市の概要について整理しておきましょう。
・長野県の北部、長野盆地に位置する都市で、1897年(明治30年)に市制施行された。
・市の中央部では千曲川と犀川が合流し、北部・西部では山地や丘陵地が占める。
・豪雪地帯が多く、1998年(平成10年)には冬季オリンピックが開催され一躍脚光を浴びた。
・善光寺、川中島古戦場など歴史的な観光名所が多数存在するとともに、自然豊かなスポットも多く、全国から観光客が大勢訪れる。
・産業面では信州リンゴをはじめとする果樹栽培が盛んで、県下のリンゴ栽培の中心である。
基本データ
 長野市の基本データを算出しました。
長野市の基本データを算出しました。
面接で具体的な数値を聞かれることもあるので、しっかり押さえておきましょう。
面積
・総面積…約835㎢
・可住地人口密度…約1200人/㎢
人口統計
・人口総数…約36万6000人
・年少人口率(15歳未満)…約11%
・生産年齢人口率(15~64歳)…約58%
・高齢人口率(65歳以上)…約31%
・人口1000人当たりの人口増減数…約-8.7人
・外国人人口数…約4000人
・転入者数…約1万1000人
・転入率(人口1000人当たり)…約30人
・転出者数…約1万1000人
・転出率(人口1000人当たり)…約31人
※最新のデータに基づいて算出
財政状況
・歳入額…約1670億円
・歳出額…約1610億円
・地方税…約610億円
・財政力指数…0.71
・実質公債費比率…5.2%
・将来負担比率…約21%
・経常収支比率…約92%
・地方交付税依存度…13.8%
※最新のデータに基づいて算出
各種産業の特徴

長野市の各種産業についても整理しておきましょう。
農業・水産業
・長野市は日本海側気候と中央高地気候の間のような気候で、夏は暑く、冬は気温が氷点下まで下がるのが特徴である。
・そのような気候を活かし、農業ではソバや野沢菜、リンゴなどの生産が盛んに行われている。特にソバは、冬の厳しい気候に耐えられる作物として昔から栽培が行われ、長野県を代表する観光資源になった。野沢菜も長野市の特産物として知名度が高く、様々な郷土料理に活用されている。
・リンゴは明治期から栽培されるようになり、昭和の初め頃から養蚕の転換作物として本格的に育てられるようになった。長野の日照時間の長さと寒暖差が栽培に適しており、全国でも有数のリンゴの産地として有名である。
・林業や畜産業にも積極的で、特に昭和中期に植栽された人工林が豊富にあり、長野市産の木材は全国で幅広く活用されている。
工業・産業
・長野は県全体として戦前から繊維王国として有名な地域である。全国でもいち早く器械製糸を導入し、養蚕業が盛んに。さらに近隣地域の繊維工場との連携も深く、県北部に位置する長野市は北陸地方や群馬県の工場への製品提供が多く行われてきた。長野市に繊維加工工場が多くあるのは、その頃から脈々と受け継がれてきたノウハウがあるからといえる。
・近代に入ると製糸業だけでなく、食料品や印刷、電子デバイス、情報通信機器関連など様々な分野に広がり、特に繊維工業で培った技術は、コンピュータ関連の電子機器、医療分野、カメラや時計など精密機器などの分野にも活用された。
・長野県が「テクノハイランド構想」を立案し、長野市周辺を「善光寺バレー」に指定したことで産学官連携による新技術の研究開発が進められました。中でも、長野市と信州大学とのカーボンナノチューブに関する共同研究は一定の成果を上げており、「ナノカーボンを利用したスマートデバイス」の開発や製品化が日夜進められている。
・その他の分野では、スキーやスノーボード関連の製造が盛んな点も長野市の産業における特徴である。1912年(明治45年)創業の「小賀坂スキー製作所」は、日本初のスキー用品メーカーで、当時は宮内省の命を受けてスキー製造を行っており、2012年(平成24年)には創業100周年を迎えた。
商業・サービス業
・江戸時代には人や牛馬による陸上流通の他、河川を利用した船による運搬が頻繁に行われ、麻や畳糸、塩、米、酒などの物資が移入されていた。
・明治維新後、1897年(明治30年)の市制施行において長野市が県内初の市として誕生し、1888年(明治21年)〜1911年(明治44年)にかけて発達した主要幹線鉄道の普及により、長野駅周辺の幹線沿いは近代的市街地として形成されていった。
・戦後、1960〜70年代の高度経済成長期には、「長野卸センター」(現「協同組合長野アークス」)、「青果水産物市場団地」(現「長野地方卸売市場」)や工場団地の誘致が積極的に行われ、中心市街地にも百貨店など多くの商業施設が開業した。政治・経済・文化面における拠点としても急速に発展してきた。現在でも長野駅周辺には、「MIDORI長野」「ながの東急百貨店」「ショッピングプラザagain」などの商業施設があり、ショッピングを楽しめる。
・1997年(平成9年)の北陸新幹線の開通は、交通面における利便性はもちろん、経済面及び観光業の向上にも大きく寄与した。さらに1998年(平成10年)には、長野市を中心に「冬季オリンピック競技大会」が開催され、以後、国際会議観光都市として様々な集会やイベントが誘致・開催されるようになった。
・近年は、人口減少や市街地における商業機能の空洞化が問題視されているが、商店会と行政が連携した魅力ある地域社会づくりの推進が期待されている。
総合計画・基本構想等

自治体において「総合計画」や「基本構想」など呼ばれているものは、自治体の指針となるものです。
まずは簡単にでもいいので全体に目を通し、その自治体が目指している方向性などの全容を掴むことがポイントです。
その後は、あなたの興味・関心に合わせて個別の計画や取組についても調べてみてください。
隣接する市
公務員試験の面接では、近隣自治体との比較について聞かれることが多々あります。
特に隣接する市は比較対象として挙げられやすいため、下記の自治体についても目を通しておくようにしましょう。
長野県
所属する都道府県
市役所を受験する場合でも、その自治体が所属する都道府県について聞かれることがあります。
志望先の関連情報として押さえておきましょう。