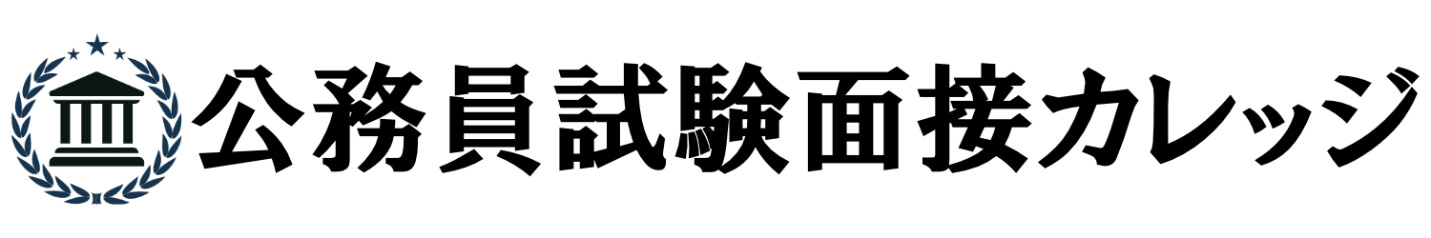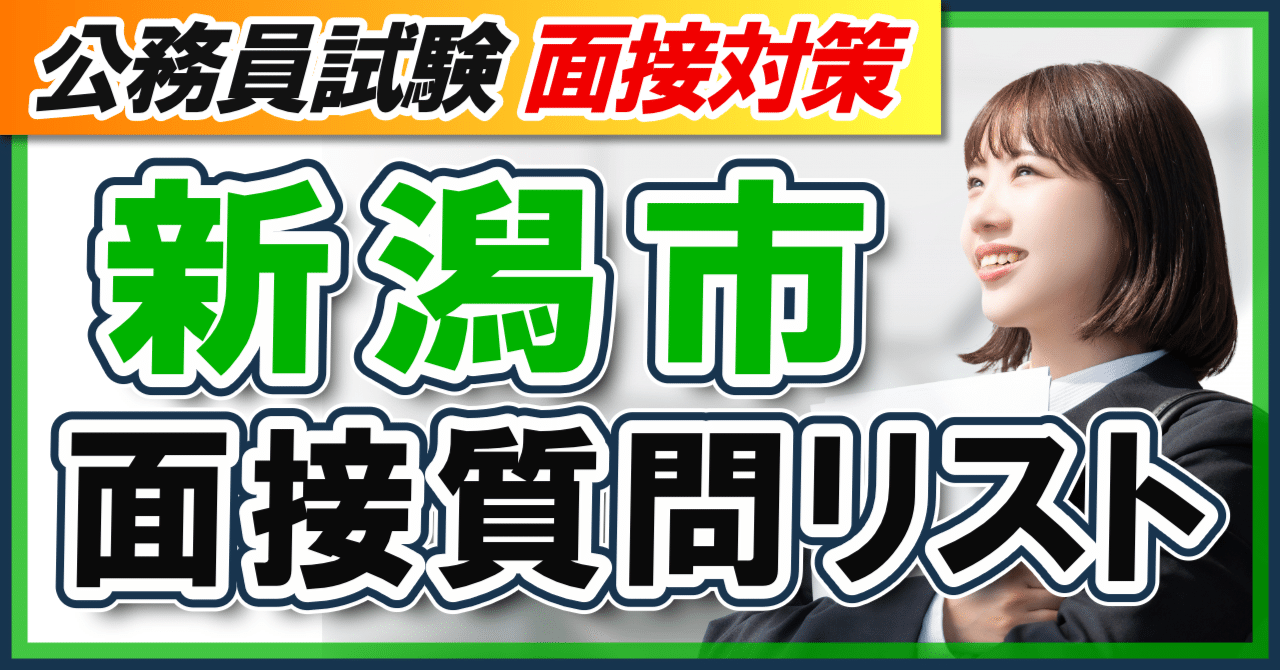新潟市役所の面接対策で重要な、市の概要、基本データ、各種産業の特徴、総合計画・基本構想等、面接カード、近隣自治体について掲載しています。
公務員試験の面接対策においては、まずは志望自治体に関連する基本的な情報を押さえることが大切です。
面接で聞かれ得るというのはもちろんですが、志望自治体や業務への理解を深めるために大いに役立つからです。
そして、そうした情報を面接での回答に活用することができれば、面接官に対してより説得力のある説明ができることでしょう。
この記事を通して志望自治体ならではの特色を理解し、ぜひ面接対策に活かしてください。
なお、その他の自治体については下記の記事からご確認いただけます。
市の概要
 市の全体像を把握するため、新潟市の概要について整理しておきましょう。
市の全体像を把握するため、新潟市の概要について整理しておきましょう。
・新潟県の県庁所在地で、新潟県中央部を流れる日本最長の川・信濃川と阿賀野川が合流する位置に発展した都市である。
・1889年(明治22年)に市制施行し、2007年(平成19年)に本州で初めて日本海に面した政令指定都市に移行した。
・高速道路や新幹線は首都圏と直結する陸上交通をはじめ、国際空港や国際港を擁して空・海の交通も整備され、日本海側の世界の玄関口としての役割を果たしている。
・広大な越後平野は農業、工業、商業など多彩な産業に恵まれており、近年では高層ビルが多く建ち並び、機能・景観ともに日本海側の中枢である。
・県内他都市と比べて、積雪量はそれ程多くはない。
基本データ
 新潟市の基本データを算出しました。
新潟市の基本データを算出しました。
面接で具体的な数値を聞かれることもあるので、しっかり押さえておきましょう。
面積
・総面積…約726㎢
・可住地人口密度…約1200人/㎢
人口統計
・人口総数…約76万8000人
・年少人口率(15歳未満)…約11%
・生産年齢人口率(15~64歳)…約58%
・高齢人口率(65歳以上)…約31%
・人口1000人当たりの人口増減数…約-8.2人
・外国人人口数…約6300人
・転入者数…約2万8000人
・転入率(人口1000人当たり)…約37人
・転出者数…約2万8000人
・転出率(人口1000人当たり)…約37人
※最新のデータに基づいて算出
財政状況
・歳入額…約4360億円
・歳出額…約4280億円
・地方税…約1350億円
・財政力指数…0.65
・実質公債費比率…12.1%
・将来負担比率…約123%
・経常収支比率…約94%
・地方交付税依存度…15.9%
※最新のデータに基づいて算出
各種産業の特徴

新潟市の各種産業についても整理しておきましょう。
農業・水産業
・新潟県は北陸地方最大の人口を有する市で、農業が基幹産業のひとつとなっている。
・二大河川(信濃川・阿賀野川)の下流部にあるため低湿で肥沃な平野が広がっていることから、市面積の約726平方kmのうち、およそ半分が農地利用されている。耕地面積は3万ヘクタールを超え、特に水田面積は全国の市町村の中で最大で、この広さは静岡・鳥取・高知の各県全体の広さを大きく上回っている。
・新潟市の農業産出額は655億円以上あり、政令指定都市の中ではトップである。また、全国市町村の中でも第3位となっている他、食料自給率が63%もあることが特徴である。政令指定都市の中での食料自給率第2位の浜松市が12%であることを見ても、新潟市の農業生産の突出ぶりが伺える。
・産出される農産物としては、コメ、チューリップ(切り花/球根)、花木(鉢物)の収穫量・出荷額が全国第1位、エダマメ、ナシ(日本梨)が第2位、ユリ(球根類)が第3位となっている。
・新潟市は日本海に面している他、二大河川の流域にあるため、古くから漁業が盛んな地域である。海面漁業の中心地は新潟港西港区の万代島であり、沿岸漁業や沖合漁業の基地となっている。
・内水面漁業では、信濃川でサケの稚魚の放流などが行なわれている他、二大河川と鳥屋野潟・佐潟、御手洗潟の湖沼が主な漁場である。
工業・産業
・北陸工業地域の中核を担っている新潟市では、多種多様な工業が盛んに行なわれており、機械工業、金属工業、製紙業、化学工業、食品製造業などが製造業の中心である。特に新潟港周辺の東区や北区、内陸部の江南区や西蒲区・南区に工場が集中しており、約41ヵ所もの工業団地が形成されている。
・経済産業大臣指定伝統工芸品である「新潟仏壇」や「白根仏壇」をはじめ伝統工芸が盛んで、新潟漆器、鯛車、亀田縞、越後花ろうそくなどが知られている。
・新潟市周辺は油田やガス田がある。市南東部の秋葉区の新津地区には、古くから原油の採取が行なわれていた「新津油田」がある。明治以降に採掘が進み、大正時代には国内で随一の産油量となり、採掘は1996年(平成8年)まで続けられた。
・新潟港には大規模な石油精製プラントが稼働し、かつては天然ガスが広く採取されていた。1999年(平成11年)まで精製業が行なわれ、市内を走る路線バスの燃料として使用されていた時代もあったほどであった。しかし、地下の天然ガスの採取によって地盤沈下が進行したため、1950年(昭和25年)代後半からは採取規制が執行され、現在でも新潟県内外の数社がガス井(ガスセイ)を設置し、天然ガスの採取を続けている。
商業・サービス業
・江戸時代の新潟は、港を中心に商業都市として活気づいた。越後国(現在の新潟県)には港が複数あったが、その中で最も賑わいを見せたのが新潟港である。その繁栄ぶりは日本海沿岸随一と称されるほどで、海へも内陸へもアクセスが良く、年貢など当時の経済活動に不可欠な米が良く採れたのが理由のひとつである。
・商船「北前船」をはじめ、元禄時代には毎年新潟港に40ヵ国・3,500艘ほどの船が出入りし、港で仕入れた商品を内陸に運ぶ運送業なども栄えた。
・幕末にアメリカら5ヵ国と幕府が締結した修好通商条約によって、新潟港が開かれたのは1869年(明治2年)である。開港後の新潟湾に来航する外国船は少なかったものの、国内物流の拠点として賑わい続けた。
・廃藩置県後、県によって同業者の独占組合である株仲間が廃止されると、新潟に進出する財閥系海運会社や回船問屋が増加した。
・大正時代には新潟港の改築工事が行われ、大型汽船が着岸可能になった。1932年(昭和7年)に「満州国」が建国されると、新潟港は満州進出の拠点になり、新潟市周辺には多くの工場が進出した。戦後の新潟港は東西に分かれ、西港は主に旅客と貨物を扱う商業港として発展し、東港は日本海側最大のLNG(液化天然ガス)取扱量を有するなど工業港としての色合いが強くなっていった。
・平成以降、市内には「新潟駅ビルCoCoLo」や「ラブラ万代」などの大型商業施設が誕生し、多くの買い物客で賑わっている。
総合計画・基本構想等

自治体において「総合計画」や「基本構想」など呼ばれているものは、自治体の指針となるものです。
まずは簡単にでもいいので全体に目を通し、その自治体が目指している方向性などの全容を掴むことがポイントです。
その後は、あなたの興味・関心に合わせて個別の計画や取組についても調べてみてください。
面接カード
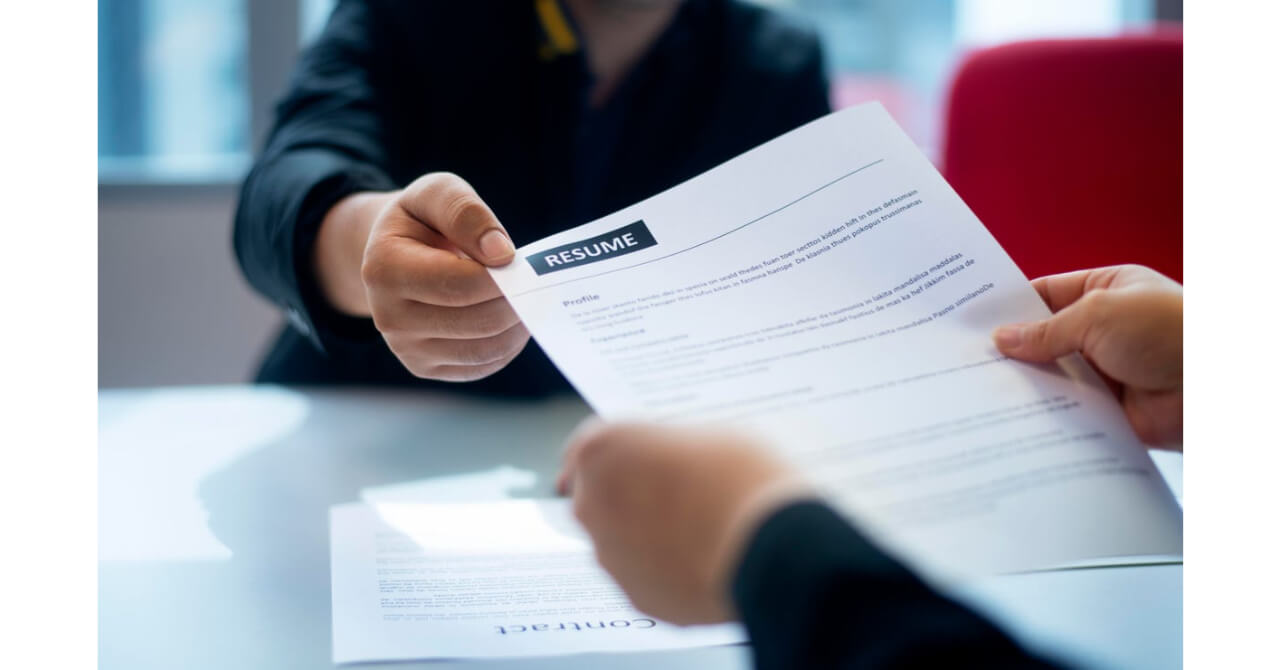
新潟市役所の面接カードの内容を掲載してているので、これを参考に実際に面接カードを作ってみましょう。
※過去のものとなりますので、あらかじめご了承ください。
・学歴
・職歴
・この試験を受けた動機、理由について
・試験に合格し、採用された場合、どんな仕事をしてみたいですか
・学校生活について(①特に研究したもの(卒業論文やゼミナールなど)②学内で参加したクラブやサークル③クラブやサークルであなたはどのような役割を果たしていましたか)
・趣味、娯楽などについて(①趣味でやっているもの②普段行っている運動)
・性格などについて(①優れていると思うところ②改善したいと思うところ③アピールポイント)
・今までに最も力を入れ取り組んできたことについて
・就職活動状況
面接質問リスト
新潟市役所の面接において、過去の受験生が実際に質問された内容をリストとして提供しています(下記のリンクからご確認いただけます)。
新潟市役所で定番の質問をはじめ、一部の受験生しか聞かれていないものの、「いざ聞かれると答えに窮する」「準備しておかなければ答えられない」ような難易度の高い質問も収録しました。
質問されることをあらかじめ把握しておけば、面接試験は決して怖いものではありません。
このリストへの回答を事前に準備することで、新潟市役所の面接試験を突破することができるでしょう。